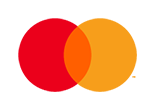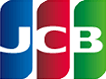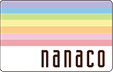糖尿病とは

糖尿病は、インスリンという膵臓から分泌されるホルモン量の不足や、働きが低下することにより血液中に含まれるブドウ糖(血糖)の濃度が高くなることで生じる病気です。こうした状態が続くと、3大合併症といわれる神経や目や腎臓などにさまざまな障害を起こし、脳梗塞や心筋梗塞と関連する動脈硬化を引き起こすことが知られています。なお、糖尿病には主に1型と2型、また妊娠中に発症する妊娠糖尿病があります。
1型糖尿病
1型糖尿病は、自己免疫系の異常などによって膵臓のβ細胞が壊れてしまい、インスリンというホルモンが分泌されなくなることで発症します。インスリンには血糖値を引き下げる効果があるため、インスリンの分泌が極度に低下する、もしくは全く分泌されなくなると、血中の糖が異常に増加し、体重減少、口渇、倦怠感、意識がもうろうとするといった重篤な症状を引き起こしかねない状態になります。これらの高血糖症状の進行する様式によって劇症1型糖尿病、急性発症1型糖尿病、緩徐進行型1型糖尿病(SPIDDM)に分類されます。劇症1型は数日単位、急性発症1型は数カ月単位で症状が進行しインスリンが必要となるため早急な治療が必要です。SPIDDMでは糖尿病の進行が緩徐なため、2型糖尿病として治療されている場合もありますが、抗GAD抗体などの自己抗体を測定することで1型糖尿病か2型糖尿病かの鑑別ができます。
1型糖尿病の治療
1型糖尿病の方は、インスリンによる治療が中心となります。インスリンにも様々な種類があり、注射回数や注射量は患者様の生活スタイル、食事、運動や年齢によって大きく異なります。インスリンポンプによる加療も選択肢の1つです。
基本的に食べてはいけない食事はありませんが、食事療法では三大栄養素(炭水化物・タンパク質・脂質)のうち、特に炭水化物の摂取は血糖値に大きく影響を与えるため、摂取する炭水化物(糖質)の量を把握することによってインスリンの必要量を調整する「カーボカウント」という方法を用いることもあります。
また血糖測定の方法や間隔も重要です。自己血糖測定(SMBG:Self Monitoring of Blood Glucose)といって患者様自身で血糖測定を行う方法と、持続血糖測定という方法もあります。主に用いられる持続血糖測定(CGM)は2週間連続して血糖値(厳密には血液中の血糖値ではなく間質液中のグルコース濃度)を測定できるため血糖値の変動が目で見てわかるようになります。
当院では、一人一人の患者様と相談しながら、それぞれの患者様にとって最適な治療を提案、提供いたします。
2型糖尿病
2型糖尿病は、いわゆる「生活習慣病」の一つで、遺伝的な体質に加え食生活や運動不足、飲酒や喫煙など日頃の生活習慣などが影響する糖尿病です。日本人の場合、糖尿病の方のうち9割以上がこの2型糖尿病です。家族や親戚などの血縁者に糖尿病の人がいる場合は糖尿病を発症する可能性が高まり、食べ過ぎ、肥満、加齢、運動不足やストレスなどが原因となります。健康な人の場合、ご飯を食べ過ぎたときにもインスリンがしっかりと機能するため、一時的に高くなった血糖値も、すぐに落ち着きます。しかし、2型糖尿病になると、インスリンの分泌が足りなくなったり、足りていてもうまく細胞に作用しなくなったりするので、血糖値が下がりにくくなります。ただし糖尿病と診断された時点で無症状の方も多く、定期的な健診や検査が重要です。悪化すると血糖コントロールが難しくなり、重大な合併症も招きやすくなりますので、早期に発見し、治療を開始することが大切です。
2型糖尿病の治療
2型糖尿病の方は、適切な食事療法と運動療法による生活習慣の見直しが治療の基本となります。これにより、目標の血糖コントロール達成を目指します。食事療法と運動療法を続けてもなお血糖コントロールが不十分な場合には、薬物療法も検討いたします。薬物療法は経口薬、注射薬、インスリンを含め多くの種類がありますので、生活スタイル、年齢、体重、合併症の程度や肝臓や腎臓の働きを確認したうえで、慎重に選択する必要があります。薬物療法を開始する場合でも少量から始め、血糖コントロールの状態をみながら慎重に調節します。生活習慣の改善により血糖コントロールが改善すれば、薬物療法の減量や中止が可能になる事もあります。薬物療法は漫然と継続するのではなく、良好な状態を目指して治療していきます。また合併症の評価も重要で眼科、歯科など必要な診療科と連携をしていきます。
妊娠糖尿病
妊娠糖尿病とは、妊娠中に血糖値が下がりにくくなる状態のことです。赤ちゃんの体重が増えすぎて難産となったり、増えすぎた羊水のため破水し早産となったり、出産後に赤ちゃんの呼吸困難や低血糖の原因となるなど、様々な危険性があります。通常は出産後に母親の血糖値は正常化しますが、将来的な糖尿病の発症リスクになることがわかっています。妊娠中は赤ちゃんのため、産後はご自身のために定期的な血糖管理と治療が必要です。
妊娠糖尿病の治療
妊娠糖尿病と診断されたら、まず食事療法による血糖値コントロールを行います。ご自身に適したエネルギー量を把握し、必要十分な量のエネルギーや栄養の摂取を心がけましょう。血糖値の上りを抑えるために、一汁三菜のバランス食を基本に、血糖を見ながら主食を分割して、1日6食に調整する『分食』を行います。適切な食事の量や栄養バランスを医師よりご提案いたします。お仕事のご事情で分食が難しい場合や、分食を行っても食後の血糖値が上がりやすい場合には、インスリン療法によって血糖コントロールを行います。妊娠すると胎盤から分泌されるホルモンの影響でインスリンが効きにくくなり、妊娠後期になるにつれて必要なインスリン量が増えていきますが出産後はインスリンを中止できることが多いです。
膵性糖尿病
慢性膵炎や膵臓の手術などによって膵臓の機能が低下し、インスリン分泌が低下することで発症します。膵臓は血糖を下げるインスリンのほか、血糖を上げるグルカゴンも分泌しますが、膵性糖尿病では両方のホルモンのバランスが崩れ、血糖値の不安定な変動を引き起こします。そのため、低血糖や高血糖を繰り返しやすく、管理が難しいのが特徴です。また、慢性膵炎が原因の場合、膵外分泌機能の低下による消化不良や体重減少も伴うことがあります。
膵性糖尿病の治療
治療の基本は、血糖管理と膵臓の機能低下への対応です。血糖管理では、軽症例では食事療法や血糖降下薬が有効な場合もありますが、1型糖尿病に準じて強化インスリン療法が中心となります。また、消化吸収を助けるために膵酵素製剤を併用することもあります。食事療法では、急激な血糖変動を防ぐために、炭水化物の摂取量や食事の回数を調整することが重要です。さらに、血糖変動を把握するために自己血糖測定や持続血糖測定を行い、適切な管理を継続していくことが大切です。
インスリンポンプ療法(皮下持続インスリン注入療法:CSII)について
インスリンポンプとは
持続皮下インスリン注入療法(CSII)は、小型のポンプにより持続的にインスリンを皮下注入して血糖管理を行う治療法です。このポンプをインスリンポンプと言い、皮下に留置したカニューレという細い管を通して自動的にインスリンが注入されます。食事や生活状況に合わせて単位調節しながら追加インスリンをボタン操作で注入することができます。
当クリニックでもインスリンポンプによる治療を行っております。
インスリンポンプの仕組み
- 基礎注入(ベーサル):(超)速効型インスリンを基礎インスリンとして24時間持続的に注入し、安定した血糖コントロールを維持。
- 追加注入(ボーラス):食事時や血糖値が上昇した際に、手動で追加インスリンを注入。
- CGMとの連携:一部のポンプでは持続血糖測定(CGM)と連携し、リアルタイムで血糖値をモニタリングして自動的にインスリン量を調整できるSAP療法も可能。
メリット
- 血糖コントロールの向上:インスリンを細かく調整でき、HbA1cの改善、質の高い血糖管理が期待できる。
- 低血糖リスクの軽減:インスリンの過剰投与を防ぎ、特に夜間低血糖を回避しやすい。
- 生活の自由度向上:食事時間や摂取量を柔軟に調整可能。
- 注射回数の削減:1日に複数回の注射が不要。
デメリット
- 費用:ポンプ本体や消耗品のコストがかかる(健康保険適用あり)。
- 皮膚トラブル:カニューレ装着部の発赤や感染リスク。
- 管理の手間:ポンプの操作や消耗品の交換が必要。
- 緊急時のリスク:機器の故障、カニューレ、チューブの外れや詰まりによる高血糖やケトアシドーシスの危険性。
インスリンポンプ療法のよい適応
- 高血糖や低血糖を繰り返すなど、血糖管理が不安定な場合
- 無自覚低血糖が頻回に起こる場合
- 妊娠糖尿病でインスリン治療が必要な場合
- 暁現象(夜間・早朝の血糖値上昇)が顕著な場合
などが考えられます。また1日中カニューレを皮膚に装着し、ポンプ本体を帯同することに抵抗感が少なく、機器の操作ができる方が対象となります。
糖尿病の合併症について
糖尿病の三大合併症とは、神経障害(し)、網膜症(め)、腎症(じ)の3つを指し、「し・め・じ」と覚えます。
糖尿病の初期には自覚症状がないことも多いですが、血糖値が高い状態が長く続くことで、全身の細かい血管や末梢神経がダメージを受け、様々な合併症を引き起こします。
これらの合併症は、放置すると足の切断、失明、人工透析などにつながる可能性があるため、早期発見・早期治療が重要です。糖尿病と診断されたら、合併症の有無についても定期的に検査を受けるようにしましょう。
三大合併症

神経障害
高血糖によって末梢神経が障害されることで、様々な症状が現れます。
神経障害の症状は、足先のしびれや痛み、感覚の感じにくさ、冷えなどが挙げられます。自律神経障害を伴う場合は、胃腸の動きが悪くなることによる胃もたれ、便秘や下痢、起立性低血圧、発汗異常、排尿障害なども起こることがあります。
神経障害の治療の基本は、血糖値の改善です。適切な食事療法、運動療法、薬物療法を行い、血糖値を正常範囲に近づけることで、症状の進行を抑えることができます。また、症状に合わせて、痛みを和らげる薬物療法が用いられます。

網膜症
血糖値が高いことによって網膜の細い血管が障害されることで、視力低下や失明に至る可能性のある合併症です。初期には自覚症状がない場合が多く、気づかないうちに病状が進行していることもあるので定期的な眼科受診が必要です。
病状が進行すると、かすみ目、視力低下、視野の欠損、などの症状が現れます。さらに悪化すると、網膜剥離や硝子体出血などを引き起こし、最悪の場合失明に至ることもあります。
網膜症の治療法は、病状の進行度合いによって異なります。初期の段階では、血糖値の改善が重要です。進行した網膜症ではレーザー光凝固や硝子体手術などの外科的治療や、抗VEGF療法といった薬物療法が必要となる場合もあります。

腎症
高血糖によって腎臓の血管が集まっている糸球体が損傷を受け、腎機能が低下する合併症です。
腎症の初期は自覚症状があまりなく、症状を自覚したときには既に病状が進行しているというケースも少なくありません。腎症が悪化すると余分な水や尿毒素が体にたまることにより、むくみやだるさなどの症状が現れます。末期腎不全になると呼吸困難感が出現し、透析や腎移植が必要になります。
定期的な尿検査や血液検査で早期発見することが重要です。
腎症の治療の基本は、適切な食事療法、運動療法、薬物療法を行い血糖値、血圧、コレステロール、尿酸などを正常範囲に近づけることです。
食事療法ではたんぱく制限やカリウム制限などの食事療法を行う場合もあります。また薬物療法ではRA系阻害薬やSGLT2阻害薬などによる治療が腎症の進行抑制に有効であることが分かっています。
糖尿病のその他の合併症
血糖値が高い状態では血管の内皮細胞を傷つけ、動脈硬化を促進します。動脈硬化は血管が硬くもろくなる状態で、脳梗塞や心筋梗塞、末梢動脈疾患などのリスクを高めます。糖尿病患者はそうでない人に比べて動脈硬化のリスクが2~4倍高いと言われています。
脳梗塞、心筋梗塞
糖尿病は喫煙、高血圧、脂質異常症などともに脳梗塞、心筋梗塞のリスクを高める重要な因子です。
動脈硬化によって脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳組織への血流が届かなくなり、脳細胞が壊死してしまう病気が脳梗塞です。また心臓の血管(冠動脈)が動脈硬化によって狭くなったり詰まったりすることで、心筋への血流が途絶えることで心筋が壊死してしまう病気が心筋梗塞です。
足壊疽
糖尿病の合併症である神経障害や末梢動脈疾患によって足の血行が悪くなり、足の組織が壊死してしまう病気が足壊疽です。糖尿病患者に多くみられる合併症で、最悪の場合、足の切断に至ることもあります。傷の治りが遅いため、小さな傷でも細菌感染を起こしやすく、壊疽に進行しやすくなります。
当院ではフットケアで足を清潔に保つお手伝いをしています。
糖尿病合併症の予防と対策
糖尿病の合併症は、血糖値が高い状態が続くことで血管や神経が損傷を受け、様々な体の不調を引き起こします。糖尿病の治療の目標は合併症を予防し、糖尿病でない方と同じ健康な生活を送ることです。そのためには日々の生活習慣の見直しと適切な治療が不可欠です。
血糖値を良好に保つことが最も重要であり、食事療法、運動療法、薬物療法などを組み合わせて、多角的にアプローチしていく必要があります。当院では医師、看護師、栄養士など様々な職種がこれらの治療をサポートしていきます。
血糖マネジメントの重要性
血糖の高い状態が続くと、血管の内壁が傷つきやすくなり、動脈硬化のリスクが高まります。動脈硬化は、神経障害(し)、網膜症(め)、腎症(じ)といった三大合併症だけでなく、心筋梗塞や脳梗塞などの命に関わる合併症を引き起こす原因にもなります。
血糖値を適切な範囲にすることで、これらの合併症の発症や進行を抑制することができます。血糖値の目標値は、生活状況や年齢、治療薬によって異なります。HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)と呼ばれる過去1~2ヶ月の平均血糖値を反映する指標も重要です。
当クリニックでは、院内で血糖値・HbA1c・尿検査を実施しています。
血糖値
血糖値は、血液中のブドウ糖の濃度を測定します。糖尿病は、血糖値が基準の値よりも高い状態で診断されます。血糖値検査は、糖尿病の早期発見・診断に非常に重要です。
空腹時血糖値
空腹時血糖値は、10時間以上の絶食後の血糖値を測定します。朝食前の空腹時に採血を行うのが一般的です。
随時血糖値
随時血糖値は、食事時間や絶食時間に関わらず、血糖値を測定します。食後高血糖の確認や、糖尿病の症状が現れた際の迅速な診断に役立ちます。
75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)
75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)は、75gのブドウ糖を溶かした水を飲み、一定時間後の血糖値の変化を調べる検査です。糖尿病の診断、特に境界型糖尿病(糖尿病予備軍)の診断に有用です。この検査では、ブドウ糖を摂取した後の血糖値の上昇具合や、体内のインスリン分泌などを評価することができます。検査には2時間程度かかり、複数回の採血が必要です。
血糖値の基準値
血糖値の基準値は、検査の種類によって異なります。空腹時血糖値では、126mg/dL以上が糖尿病型、110~125mg/dLが境界型(糖尿病予備軍)とされています。随時血糖値では、200mg/dL以上が糖尿病型と診断される目安となります。75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)では、2時間後の血糖値が200mg/dL以上で糖尿病型と診断されます。
また自覚症状がある場合や糖尿病網膜症がある場合にはそれらも総合的に考慮して診断されます。
HbA1c
HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)は、過去1~2ヶ月の平均的な血糖値の状態を反映する検査です。血糖値は日々変動しますが、HbA1c検査では、より長期的な血糖コントロールの状態を把握することができます。糖尿病の診断、治療効果の判定、合併症の予防に不可欠な検査です。
HbA1cとは、赤血球中のヘモグロビンにブドウ糖が結合したものです。赤血球の寿命は約120日であるため、HbA1cの値は過去1~2ヶ月の平均的な血糖値を反映します。血糖値が高いほど、ヘモグロビンとブドウ糖が結合しやすくなり、HbA1cの値も高くなります。
HbA1c検査は、採血によって行われ、比較的簡便な検査で、10分程度で結果が出ます。
HbA1cの基準値
HbA1cの基準値は、一般的に以下の通りです。ただし、検査機関や使用する機器によって若干の差がある場合があります。
正常値:4.6~6.2%
糖尿病型:6.5%以上
家族に糖尿病の方がいる場合や肥満、高血圧、脂質異常症などがある方はHbA1c 5.6%以上、それ以外の方もHbA1c6.0%を超える場合は将来糖尿病に移行しないか注意する必要があります。生活習慣の改善や定期的な検査が必要です。
尿検査
尿検査では、尿中に含まれる様々な成分を調べることで、腎臓の機能や合併症の有無を確認できます。糖尿病の合併症に関連する主な項目は以下の通りです。
- 尿糖:健康な状態では、尿中に糖はほとんど検出されません。しかし、血糖値が一定以上高くなると、尿中に糖が排出されるようになります。SGLT2阻害薬という糖尿病の薬を内服している場合にも尿糖は陽性となります。
- 尿蛋白:健康な人でも微量の蛋白が尿中に排出されることがありますが、腎臓に障害があると、尿中に排出される蛋白量が増加します(蛋白尿)。糖尿病性腎症の早期発見に重要な指標となります。
- 尿ケトン体:炭水化物量が不足や、必要なインスリンが不足すると、体内の脂肪が分解されてケトン体が生成されます。ケトン体は尿中に排出されるため、尿ケトン体の有無は、糖尿病ケトアシドーシスのリスクを評価する上で重要な指標です。
- 尿潜血:尿中に赤血球が混じっている状態です。腎臓や尿路系の炎症や結石、腫瘍などが疑われます。