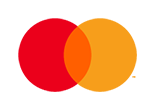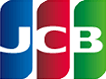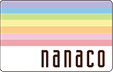腎臓内科とは

腎臓とは腰のあたりの背中側に左右一つずつあるそら豆のような形をした臓器です。
腎臓には、体内の老廃物を尿として排出する機能、体内の水分バランスを調整する機能、血圧を調整する機能、血液をつくる機能など、生命を維持するための様々な重要な機能が備わっています。
腎臓病は早期発見、早期治療により治癒する可能性が高くなりますが、放置してしまうと腎不全を引き起こし、人工透析が必要となる場合もあります。気になる症状がある、健康診断等で異常を指摘された場合には、お早めの受診をお勧めいたします。
このような症状の方は
ご相談ください
- 健診で腎機能障害、腎機能低下を指摘された
- 血尿
- 頻尿や夜間の尿意
- 尿の色や濃さが変わった、尿が泡立っている
- 浮腫み
腎臓内科の主な疾患
慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease: CKD)
CKDの患者様は1300万人以上(成人の8人に1人)いると推計され、新たな国民病とも言われています。CKDとは腎臓のはたらきが健康な人の60%未満に低下する(eGFRが60ml/分/1.73m2未満)か、蛋白尿が出るなどの腎臓の異常が3カ月以上続いている状態を言います。初期にはほとんど自覚症状がありませんが、進行するとむくみ、夜間頻尿、倦怠感、貧血、息切れなどの症状が出現します。
CKDの早期では進行を遅らせることが出来ますが、あるレベルまで悪くなってしまうと自然に良くなることはなく、放っておくと進行し、人工透析や腎移植が必要となる可能性があります。またCKDがあると脳卒中や心筋梗塞など心血管病発症リスクが高まるため早期発見、早期治療がとても重要です。高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満やメタボリックシンドロームはCKD発症や進行のリスクとなるため、自覚症状がなくても定期的に血液検査、尿検査を行うことが大切です。治療は、日ごろの生活習慣の改善、塩分制限や食事療法、薬物療法による血圧管理、貧血の改善、脂質管理、血糖管理などを総合的に行います。またCKDの合併症に応じた適切な治療をするために、定期的な検査も重要になります。
糖尿病性腎症
糖尿病性腎症は糖尿病の合併症で、最も重要なCKDのひとつです。糖尿病で血糖値が高い状態が長く続くことで、全身の動脈硬化が進み毛細血管の塊である腎臓に影響が出てきます。そのまま放っておくと腎機能が低下し、数年~数十年の経過で人工透析や腎移植が必要な末期腎不全という状態になってしまいます。糖尿病性腎症は段階的に進行するので、できるだけ早期に糖尿病の治療をすることで進行を遅らせることができます。末期腎不全で透析導入となる原因の1位は糖尿病性腎症です。
腎硬化症
腎硬化症は長期間の高血圧や加齢を原因とするCKDのひとつで、透析導入の原因として増えてきており、近年では第2位となっています。高血圧は腎不全を引き起こす一方で、いったんCKDが発症すると高血圧が重症化するという悪循環が起きるため、悪化する前にきちんと高血圧治療を行うことが大切です。
腎性貧血
腎臓はさまざまなホルモンを分泌しています。その中のひとつに赤血球をつくるはたらきを促進するエリスロポエチンというホルモンがあります。腎臓のはたらきが低下すると腎臓からのエリスロポエチンの分泌が減り、赤血球をつくる能力が低下することで貧血になります。このようにしておこる貧血を「腎性貧血」といいます。腎性貧血に対しては、鉄不足がないことを確認し、エリスロポエチン製剤やもしくはHIF-PH阻害薬を用いて治療をします。